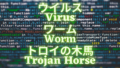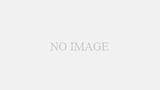菅政権が少人数学級の導入を教育改革の柱とするようです。

9月8日に文科省で開かれた小中高校の教育を考える会議の初会合でも萩生田光一文科相は、
令和時代のスタンダードとしての「新しい時代の学びの環境の姿」と、特に少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備や、関連する施設整備等の環境整備の在り方について議論いただきたい
と言及していました。
- そもそもの少人数学級とは何か?
- その実施によるメリットとデメリットは?
- たまに聞かれる少人数指導とはどう違うのか?
これについて説明していきます!
※少人数学級が学力向上につながるかどうかについては、以下の記事で紹介しています!

少人数学級とは何か
まず、公立学校の学級人数はどのように決められているのかを確認しましょう。
公立小中学校の学級編制は義務教育標準法という法律をもとにして決められています。
推移をみてみると
1959年度 50人
1964年度 45人
1980年度 40人
2011年 小学1年生のみ35人
2012年 学級編成に変更なし。教員配置増加
施行されたのが60年ほど前で、時代も変化していますし、もっと変更されてもいいかとは思いますが、現段階でこれ以上の変更はありません。
ちなみに私が勤務していた学校では1クラス45人学級が多く、机の間隔がとても狭かったのを覚えています。
30人クラスでやっと間隔にも余裕がみえてきますね!
話を戻しましょう。
この義務教育標準法で定められている数より少ない学級を少人数学級といいます。
政府はこの学級編制を30人くらいにしようと考えているわけです。
少人数指導との違いは何か
では、少人数学級と少人数指導はどう違うのでしょうか?
①少人数学級:学級そのものの人数を少人数にする
②少人数指導:特定の教科指導時の人数を少人数にする
たとえば従来ならば、
クラスは40人
↓
数学はαクラスとβクラスに20人ずつ分かれる
ということをした場合、この数学の授業は少人数指導になります。
中学校や高校で選択授業ってありませんでした?
あれも少人数指導です。
あのイメージを持っていただくとわかりやすいと思います!
このように特定の授業(=教科指導)を受ける児童生徒の数を少なくすることを少人数指導といいます。
ちなみに塾も各教科、習熟度別でクラス分けをしているため少人数指導にあたりますね!(少人数指導という言葉を使ったことはほとんどないですが)
それに対してクラスの人数そのものを少なくするというのが少人数学級になります。
少人数学級からさらに少人数指導を導入するもいいですし、そのままの人数で授業をするのもいいですね。
少人数学級を導入することのメリット
少人数学級を導入したい理由とも言えますね。
3点挙げます。
- コロナ対策として児童生徒間の距離を保つ
- 個々の児童生徒に対して細かく対応できる
- 教員の負担を減らす
コロナ対策として児童生徒間の距離を保つ
今回、新たに提起された理由です。
政府もこれを一番目の理由としているようです。
安全の確保という点では、もちろん間違っていません。
しかし、教員の方々の中には「そこ?」と思う方もいるかもしれません。
なぜなら、少人数学級は随分と昔から提唱され続けているからです。
個々の児童生徒に対して細かく対応できる
学習の習熟度は児童生徒によって、まちまちです。
その習熟度の差が大きいと、先生方も思うように授業ができません。
1人だけならまだ対応できるかもしれませんが児童生徒の数が多くなると、そうもいかないものです。
だから、少人数学級にすれば、児童生徒たち全員に対応できるため、望む声が後を絶ちません。
私も適正な人数は30人が限界かなと考えています。
より少ないならば、全員に声かけもできるでしょう。
教員の負担を減らす
(授業中の負担が主だと思いますが)教員の負担も減らすことができるため、少人数学級を望む声が多いです。
私は、ここについては一概に言えない点も多いかなと思います。
というのも、40人では十分に対応できない分、かりに20人にとても丁寧にノート点検をしたために、労働時間が同じくらいかかるなら、負担が減ったとは言えないからです。
担当教員にとっては、少ない人数の児童生徒を細かくみる方がいいという声は多いとは思いますし、それは悪いことではないです。
あくまでも負担という観点でみるならば、負担が減ったとは言い切れないということです。
少人数学級を導入することのデメリット
いいことづくしのようにみえる少人数学級ですが、必ずしもいいことだけではありません。
3点紹介します。
- 教員の質と数の確保
- 教室数の確保
- 児童生徒の価値観の固定
※少人数学級が学力向上につながるかどうかについては、以下の記事で紹介しています!

教員の質と数の確保
一番の問題はここでしょうね。
もともと1つのクラスを2つに分割した場合、2クラスになるわけですから教員も2人必要です。
また数だけ合わせればいいわけでもありません。
指導力のある教員が必要です。
必要な分の財源を確保して、正規雇用の教員を増やすか、非常勤講師(=非正規雇用)を雇うのかは自治体次第ですが、この課題を乗り越えることがカギになります。
教室数の確保
当たり前ですが、授業をするには教室が必要です。
少人数学級を導入した分だけ教室が必要になってきますが、空いている教室だけでまかなうことができる学校はどれだけあるか…
教室を新設するならば、その分のコストもかかりますからね。
ここまでコスト面の話になってしまいますが、財務省からいかに財源を確保できるかにかかっています。
児童生徒の価値観の固定
意外と注目されないですが、この問題もあると思います。
私立学校と比べて公立学校には多種多様な価値観をもつ児童生徒が通います。
ここをどう捉えるかは人それぞれですが、私は公立学校のいいところだと思っています。
あまり早い段階で価値観が固定されると、年齢を重ねた後に自分と価値観が合わない人と対峙したときにうまく対応できないかもしれません。
無理に合わない人と仲良くしろというわけではないですが、この経験も必要だと思うのです。
考えられる対策はクラス替えを多くするなどして、固定を防ぐことです。
まとめ
以上、少人数学級について紹介してきました。
それぞれのメリットとデメリットを踏まえた上で今後どのように導入していくかの議論を進めてほしいですね。